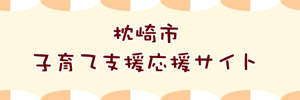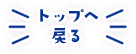本文
育児・介護休業法が改正されます(順次施行)
児・介護休業法が改正されます(令和7年4月1日)
仕事と育児・介護との両立がしやすい職場環境づくりをさらに進めるため、育児・介護休業法が改正されました。
事業主の皆さんに取り組んでいただく必要がある事項を紹介します。
1 令和7年4月1日からの主な改正点
(1)子の看護休暇の対象となる子の年齢が小学校3年生修了時までに拡大されるとともに、学級閉鎖、入学式などのために取得できるようになります。
(2)所定外労働(残業免除)の対象となる子の年齢が小学校就学前までに拡大されます。
(3)研修の実施、相談窓口設置など、介護関係制度を取得しやすい職場環境づくりのための措置を行うことが事業主の義務になります。
(4)介護に直面した労働者または40歳に達する労働者に対して、事業主が、個別に仕事と介護の両立支援制度等を周知し、また、介護休業等を取得するかどうか意向を確認することが義務になります。
(5)子の看護休暇及び介護休暇の対象となる労働者から、勤続6か月未満の労働者を除外する仕組みが廃止されます。
(6)常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、育児休業取得率を公表することが義務になります。
(7)常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定または変更するとき、男性の育児休業等の取得状況及び労働時間の状況を把握するとともに、把握した状況に係る数値目標を設定することが義務になります。
2 令和7年10月1日からの主な改正点
(1)3歳から小学校に入るまでの子を持つ労働者が利用可能な、始業終業時刻の変更など柔軟な働き方を実現するための制度を2つ以上導入することが事業主の義務になります。また、3歳になる前の子を持つ労働者に対して、事業主が、柔軟な働き方を実現するための制度の内容を個別に周知し、制度を利用するかどうか意向を確認することが義務になります。
(2)労働者本人または労働者の配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者と、3歳になるまでの子を養育する労働者に対して、事業主が、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取した上で、意向について配慮することが義務になります。
3 チラシ
詳細は育児・介護休業法改正ポイントのチラシをご確認ください。
育児・介護休業法改正ポイントのチラシ [PDFファイル/1.39MB]
令和4年4月1日から段階的に改正されています
1 令和4年4月1日からは、以下の点が変わりました
(1) 事業主は、研修の実施、相談窓口設置など育児休業を取得しやすい職場環境づくりのための措置を行うことが義務になります。
(2) 労働者から本人または配偶者の妊娠・出産について申し出を受けた事業主が、その労働者に対して、個別に育児休業に関する制度等を周知し、また、育児休業を取得するかどうか労働者の意向を確認することが義務になります。
(3) 期間を定めて雇用される労働者が育児休業または介護休業を取得する際の、勤続1年以上の要件が廃止されます。
2 令和4年10月1日からは、以下の点が変わりました
(1) 「産後パパ育休」が新設されます。子の出生後8週間以内の4週間以内で、2回に分割して育児休業を取得できるようになります。
(2) 「産後パパ育休」以外でも、育児休業を1歳までの間に2回まで分割して取得できるようになります。
(3) 1歳以降の育児休業を、夫婦で交代して取得できるようになります。また、やむを得ない事情がある場合は、再度取得できるようになります。
3 令和5年4月1日からは、以下の点が変わりました
常時雇用する労働者数が1000人を超える企業は、育児休業取得率を公表することが義務になります。
お問い合わせ
育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の詳細な内容等については鹿児島労働局ホームページ<外部リンク>もしくは鹿児島労働局 雇用環境・均等室(電話099-223-8239)まで。