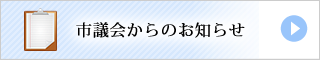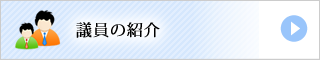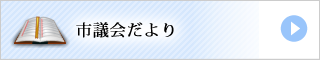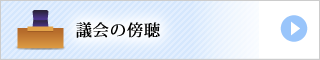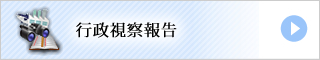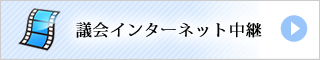本文
議会からのお知らせ
定例会・臨時会等のお知らせ
次の日程が決まりましたら、お知らせします。
傍聴についてのお願い
- 議場に入場する際は、階段下に備え付けてある消毒液にて、手指の消毒をお願いいたします。
- 傍聴の際は、マスクの着用にご協力ください。
- 手洗いや咳エチケットなど、感染防止対策にご協力ください。(「咳エチケット」とは、咳、くしゃみの際に、マスク、ティッシュ、ハンカチ、袖などで口や鼻を押さえることをいいます。)
- 咳や発熱などで体調の優れない方は、傍聴をご遠慮いただきますようお願いいたします。
- 本会議はインターネットで生中継及び録画映像の配信をしておりますので、ご利用ください。
- 傍聴席は31席設けてありますが、座席数より傍聴者が多い場合には傍聴をお断りする場合がございます。
議員定数適正化及び議員報酬等調査(令和7年12月19日)
議員定数適正化及び議員報酬等調査特別委員会では、枕崎市議会の最高規範である枕崎市議会基本条例を尊重し、同条例第20条及び第21条に定める議員定数及び議員報酬の規定と整合性を図りながら調査検討を行いました。
調査報告書については、以下のとおりです。
日米地位協定の見直しを求める意見書
在日米軍の地位や施設・区域の使用について定めた条約である日米地位協定は、1960年(昭和35年)に日米間で締結されて以降、一度も改定されていない。
1995年(平成7年)9月に沖縄本島北部で発生した少女暴行事件を契機に、その問題点が明らかになり、同年11月、沖縄県は見直し要請を日米両政府に初めて行った。2018年7月及び2020年11月には、全国知事会による「米軍基地負担に関する提言」が決議されている。提言では、「日米地位協定を抜本的に見直し、米軍機の飛行について最低安全高度を定める航空法令や航空機騒音の環境基準を定める環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させること、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること」などが明記されている。
日本の航空法は、航空機の最低安全高度を人口・家屋密集地域では最も高い障害物から300メートル、その他の地域では150メートルと定めている。日米地位協定により米軍にはこの規定は適用されないものの、1999年1月の日米合同委員会で、日本の航空法と同じ高度基準を米軍機にも適用すると確認されている。しかしながら、低空飛行は各地で目撃され、本県においても米軍機の可能性ありと国から回答があった目撃情報は、直近の2023年度には200件、2024年度の4月から6月だけでも81件に及んでいる。
2023年11月に発生した屋久島沖でのCv22オスプレイの墜落事故でも、政府による立ち入り調査はできていないことから、これまでの日米地位協定の運用面での改善ではなく、全国知事会の提言に沿った協定の見直しがなされることで、日本と米国が対等な立場で互いに主権を認め合うことにつながるものである。
さらに、全国市長会においても日米地位協定の見直しに関する要望がなされている。
よって、国におかれては、国民の生命・財産と人権・環境を守る立場から、日米地位協定を見直しされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年9月25日
鹿児島県枕崎市議会
ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための令和8年度政府予算に係る意見書
学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置など解決すべき課題が山積しており、子供たちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠である。
令和7年3月31日に成立した令和7年度予算では、小学校における教科担任制が第4学年まで拡大されたが、鹿児島県における配置数は100人にも届かず、教員の配置増を求める学校現場の声を反映したものとはなっていない。さらに、少数職種の加配等を含め「様々な教育課題への対応」として文科省が求めていた配置数も減じられたままである。また、教員採用試験の受験倍率の低下や離職者・病気休職者の増加等によって、学校現場は慢性的な人員不足状態にある。
教育の機会均等と水準の維持向上をはかるとともに、すべての子供にゆたかな学びの保障や学校における働き方改革を進めるためにも、教職員定数の改善が必要である。
よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請する。
記
1 学校の働き方改革・長時間労働改めるを実現するため、さらなる少人数学級の推進、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。
2 特別支援学級籍の子供を交流学級でも在籍児童生徒数としてカウントすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年6月27日
鹿児島県枕崎市議会
枕崎市議会に関するアンケート調査結果について
市議会では、議会のあり方について「議員定数適正化及び議員報酬等調査特別委員会」を設置し、本市の実態に即した議員定数や報酬等の調査・研究を進めているところです。
その一環として今回、市民の皆さんの市議会に対する声をお聞きする「アンケート調査」を令和3年11月に、住民基本台帳から18歳以上の市民1,000人を無作為に抽出し、調査票をお送りしてアンケート調査を実施したところ、306件の回答をいただきました。
アンケートの回答にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
アンケート結果についてご報告させていただくとともに、皆さんからお寄せいただいたご意見等は、市議会として真摯に受け止め、市議会の今後のあり方について、なお一層の調査・研究を進めてまいります。